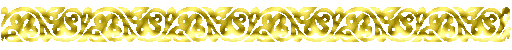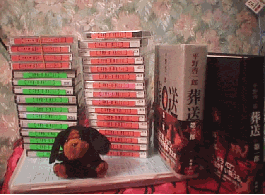|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速報 サントリーホ−ル 興奮のるつぼと化す! メンデルスゾーン・ヴァイオリン協奏曲 スロヴァキア交響楽団と共演 4月2日(水) |
ほぼ満席に近かったサントリーホールの客席。固唾を呑んで見守る中、指揮者のカーク・トレバーさんにエスコートされて、我らがナリミチの登場。 とたんに割れんばかりの拍手がホールを圧し、いつものようにかすかな微笑をたたえて演奏者の位置に立つ。 (あ、お元気そう・・・)とほっとする瞬間である。 今日はいつものリサイタルと違って「スロバキア交響楽団を聴きに来ている聴衆」も少なくないワケで、こんな時こそ成道さんの真価が問われる時・・・。そしてあらたなファン層が開ける時でもある。 ナカダは2階のRD席だったのですが、お隣にいた若いカップル、成道さんのお名前をきいたのは初めてとか。 でもメンデルスゾーンの出だしにふーっと息を呑み、二人とも身を乗り出して聴いている。 終わった時、彼女は目をうるませて「素晴らしいですねえ!」 そこでナカダはファンクラブの存在を熱をもって語る。入会してくださる手応え充分とみた。 とにかく冴え渡った素晴らしい音。スロバキア・・・も思ってたより遥かにハイレベルでとても音が柔らかい。 (新世界も今まできいた中では最も表情豊かで、ことに例の第二楽章は心を揺さぶるものがあった。アンコールのスラブ舞曲8番・10番も圧巻) 成道さんとは「音質」の面で非常に相性がいい・・・と見たのは私だけではないだろう。 さて、これから第2日目のコンサートに出かける。今日はバルトークである。カークトレバーというシェフの腕前によってナリミチという最高の食材がどんな「料理?」になって出てきてくれるのか・・・?期待満々! では行ってきます! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月3日 この感激! バルトークに聴衆、興奮 鳴り止まぬ拍手!!拍手 |
4月3日 サントリーホールは鳴り止まぬ喝采、そして「ブラボォー!」に揺れた 「神業(わざ)」とでも表現すべきか?バルトークのあの難解といわれるコンチェルトを堂々と弾き終えたあと、、なかば放心状態の聴衆に向かって、にこっとあのいつもの成道スマイルが・・・ そして極めつけ!のチャイコフスキイ。 大河の流れを思わせるような旋律がナリミチのヴァイオリンを通して会場に拡がると酔いしれた聴衆の鼓動までも巻き込んでしまうような一体感がそこに生まれた。奏者と聞き手との完全な融合! 音楽を乗せた透明な空気が大きく渦を巻き、会場を駆け巡る。 ナマの音楽でしか感じ得ないあの不思議なうねり。 「プログラム」に、カーネギーホールまで成道さんの取材に訪れた音楽ジャーナリストの 「温かな音色の輝き」と題された一文が載っているが、実に的確に、しかも優美に成道さんの音楽を表現していらっしゃるので是非読んで頂きたい。 「友沢裕子さん」とおっしゃる美しい女性ジャーナリストだが、ナカダは今夜なんとこの方のお隣の席で成道さんのコンサートの陶酔を共有する・・・という「光栄」に浴することが出来たのでありました!(ニューヨークでナカダも取材を受けたのです。それ以来、仲良くさせて頂いてます。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下室で「おしのび」の?サイン会。疲れたご様子もなく気軽に・・・ほんとうにありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 毎度オナジミ??! 毎度オナジミ??!われらが「成道の会・TOKYO」の最強メンバー??( 何が最強かって?・・・そりゃあ、成道さんへの熱いエール! この後、四谷の「某・居酒屋」でウーロン茶のカンパーイ!でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4枚目のCD・本日発売! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2003・3・21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待ちに待った4枚目のアルバム、素晴らしいですね!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、ジャケットの写真集がなんともステキ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月22日 | 哀愁の トリステ (ヴェクシー) |
ヴェクシーなる作曲家の名、初めて聞いたのですが亡くなったのが1935年といいますから、ナカダが4歳のときまで生きていたわけです。 ということは、ごく近代の作曲家ってこと。 にも拘わらず、旋律は非常にシンプルで、古き時代の良さをたっぷり聴かせてくれる。 それにしても成道さんの想いがそのままじかに伝わってくるようで、眼を閉じて聴いていると、成道さんの表情までもがありありと見えてくる。聴き終ったあと、自分がなんだかとても優しい女性に変身したような気分。一方演奏者である成道さんは「おとなの哀しみ」・・・を味わいつつ、歌いあげたに違いない・・・そんなことを思わせる一曲である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月23日 | コンソレーション (リスト) |
この曲をきくと、なぜか幼い日のことが蘇る。子どものころ、暮れ方になると訳もなしに涙がこぼれた。果てしなく拡がるあかね色の空に幾千羽ともつかぬ「こうもり」が群れをなして飛び交う。(私の生まれ故郷、台湾の夕暮れはいつもそうだった)それをじっと見ていると、大空に吸い込まれるような不安が幼い私を包んでその哀しさにひとり涙した。 でもそれは今にして思えば単なる「哀しみ」ではなく、なにものかに対する強い「憧れ」・・・でもあったような気がする。成道さんの「コンソレーション」はそうした「哀しみと憧れ」の原点に私の心を引き戻してくれる・・・。もともとはリストの6曲からなるピアノ小品集の中の1曲。(なんだそうです) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月24日 | 三つの オレンジへの恋 (プロコフィエフ) |
作曲家の「キャラ」は作品と関係するものだろうか。 思うにプロコフィエフさんってきっとお茶目な人だったに違いない。だってこの行進曲のなんともおどけた、メルヘンチックな旋律。それを又、我らがナリミチは表情たっぷりに弾きこんで、聴く人の心をそらさない。 ちなみにこの「三つのオレンジへの恋」・・・もともとはオペラとして書かれたもので、彼はその筋をイタリアの劇作家カルロ・ゴッツイから拝借したらしい。ストーリーは 「笑えば治る」という奇妙な病気にかかった王子。宴会の最中に失敗をしてしまった魔女を見て大笑いしてしまう。魔女は怒って王子に呪いをかける。 「三つのオレンジの中に閉じ込められた3人の美女に恋し、その恋が実らない限り王子の病気は治らない・・・」と。 王子は家来をつれて旅にでる。せっかく見つけた2つのオレンジを家来は「のど」の乾きに勝てず食べてしまう。最後にのこったオレンジの中の王女を助け、ふたりはめでたく結ばれて、病気も全快する・・・という、いとも無邪気な筋書き。 でも本当に不思議な旋律で、朝起きぬけに聴いたりすると耳に残って一日中リピートするのでご用心。(経験済み。事実今日がそうでした。ついどこででも鼻歌で歌ってしまう。しかも成道さんの楽しげな弓捌きまで目に浮かんでいつの間にか身体でリズムをとってしまう) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月25日 | 失望 (ヴュータン) |
この曲についての解説は成道さんご自身のコトバでジャケットのパンフレットの中に書かれているので敢えて書かない。でも、私がこの曲をきいた瞬間、いたく感じ入ったことがらが、そのままそこに書き表されていたので、 「我が意をえたり!」とばかりにニンマリしてしまった。 そう、この曲は単なる「失望」の歌ではない。哀しみのなかに秘められた「情熱」。 それこそがこの曲の主流なのだ。 成道さんの演奏に私達が魂を奪われるのは、「哀しみ」も「失望」も激しい情熱の炎(ほむら)・・・にも似たカタチで 歌いあげられ、表現されているからだと思う。 私は思う。彼がひとたび ひとを愛したら・・・おそらく古今東西のどんなラブストーリーの主人公にも劣らぬほどの 激しい恋の炎に、自らを焼き尽くすまで燃え上がるのではないかと・・・。 成道ファンのすべての人がきっとそう感じているに違いありません!! あなたは そうは思いませんか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月26日 | ウイーン風 小行進曲 (クライスラー) |
此処へきてはたと筆(KEY・タッチ?)が止まってしまった。 ジャケットの成道さんの的確な、それでいていかにも「薀蓄を傾けた」って感じの短い解説に脱帽してなーんにも書けない。 クライスラーは1962年没。勿論来日もしている。「愛のかなしみ」などの抒情美あふれる作品は成道さんの雰囲気そのものって感じ。 でもなんといってもあの「タルティーニ」作曲「悪魔のトリル」のアレンジャーとしてのすごさにはただただ敬服。 成道さんはこのウィーン風小行進曲も いかにも小粋に演奏していらっしゃる。その昔、ウィーン音楽華やかなりし頃、もし成道さんが居合わせてこのCDみたいに演奏したとしたら・・・、さぞや話題騒然だったに違いない! 宮廷の美女たちに取り囲まれ、てれたような、嬉しいような表情で立ち尽くす成道さんのお顔が眼に浮かぶ・・・これはまさにそんな演奏ですねえ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月27日 | アメリカの思い出 (ヴュータン) |
ご存知「アルプス一万尺・・・」のユーモラスなアレンジ曲。ヴィルトーゾだったヴュータンが、自分の腕前をみせるため変奏曲に書き上げた・・・とジャケットにもかかれているが、成道さんの演奏もそれに劣らず自信満々、細かなフレーズもこぼすことなくカンペキに仕上げている・・・。 この曲を弾いている成道さんはわたしの中ではかわいい少年に見えてくる。 「ねえ、ママ 聴いて聴いて!ほら、ボク、こんなにうまく弾けるんだよ!」って感じ。 音楽の神様がそばについてでもいるような弓捌き。 それにしてもダニエルさんとは、 もはや「一心同体」の感がある。あの小刻みなフレーズを一糸違わず掛け合えるなんて・・・。 カ−ネギーホールでのアンコールの感激が蘇ってくる。「ブラボー」が飛び交い、スタンディング・オベ−ションに場内が揺れた あの瞬間の歓びが! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月28日 | カヴァティーナ (ラ フ) |
いままでクラシック界にあまり足を踏み入れようとしなかった人々に、音楽の美しさ、音楽が齎す勇気、音楽で昂められ、清められる魂(それはもはや信仰の域に達してると思う)・・・そういったものを教えてくださった成道さんの功績は絶大だと思います。 そしてここに成道さんが取り上げていらっしゃる「ラフ」・・・。 「ラフマニノフ」は知っていても「ラフ」は一般的にはあまり知られていないのでは・・・?。 それもその筈、スイス生まれのこの作曲家、60年の生涯にも拘わらず、現在 演奏されるのはこのカヴァティーナ(ピアノとヴァイオリンのために書かれた)1曲だけだという。 でも、こうして1850年代に書かれた曲が成道さんの演奏で再び呼び覚まされ、21世紀の私達の心を掴む・・・。その深みのあるメロディは、数多い曲の中でも成道さんが(アルバムの中に組み入れよう・・・)とお考えになった理由(ワケ)がナットクできる・・・そんな1曲です。 ところで 私は常々、音楽と絵画との一致・・・つまり音楽を演奏する中で見えてくる情景・・・それらがひとつになって初めて「この曲は美しい!」とか「哀しい」とかを感じられる・・・というのが私的な芸術論なのですが・・・。 この曲の向こうに見えてくるのは、冷たい風のなかにそそり立つ白い鋭角の山なみ。そしてスイスの片田舎の風景。高原を横切る一筋の道を、一人の旅人・・・あたかもシューベルトの「冬の旅」に描かれたような孤独な姿の若者・・・が、それでも決然と眦(まなじり)をあげ、風に立ち向かって歩を進めている。まさに孤高という言葉そのもののように。 さて、ここからはちょっとした「パクリ(悪いコトバでゴメンナサイ)」ですが・・・・(音楽の友社・音楽辞典から拝借) ラフって人の事、みなさんにもっと知って頂きたいので。 ラフ(ヨーゼフ・ヨアヒム)は貧しい生い立ちで大学に行けず、学校の教師をしながら独学で作曲、ピアノ、ヴァイオリンを習得した。 21歳の時、メンデルスゾーンに送った楽曲が彼の推薦により大手出版社から世に出、名声を博した。リストとも親交があり、リストの交響詩の幾つかはラフの手によって管弦楽化されている。早い話、ラフはなかなか積極的で、結構 「強運」の持ち主だったのでは?(これはナカダの憶測です)その証拠にこうして成道さんによってここに改めて紹介され、今や日本中に美しい「カヴァティーナ」のメロディが流れてる・・・・。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月29日 | 東京オペラシティ コンサートホール |
今日は29日、そうです。オペラシティでのコンサートの日 (CD発売記念コンサ−ト) 素晴らしい演奏に酔いしれて来ました。 終了後、恒例の「サイン会」・・・延々続くファンの行列もお馴染みの風景です。 今日はナカダの音楽迷解説?はおやすみ。 代わりに楽しかったファンのみなさんの交流の写真を 見てくださいね。  お疲れも見せず、サインして下さる成道さん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月30日 | ハンガリア舞曲 第2番 (ブラームス) |
ブラームスの特徴と言えば、根底にジプシー音楽的なものが流れ、そして情熱的・・・。ことにハンガリア舞曲の激しさときたら。しかもほとんどすすり泣いてでもいるような「哀切の調べ」にいつしか どっぷりとつかってしまうのだ。 音楽辞典の年表には そのほかにも数限りない曲が書き記されており、ブラームスにさかれたページ数は他の作曲家よりも ダントツに多いのです。 あまり裕福な家庭環境でなかった彼は酒場での演奏で家計を助けたりしていたという。 そのうちシューマンに認められ、クララ・シューマンとも親しくなる。でも次第にクララに心ひかれるようになるのですが、音楽辞典に、そんなところまで詳しく書かれているなんて、今まで全然知りませんでした。おかげでここへきて大変勉強させられてます。 成道さんのハンガリー舞曲第二番の力強さは聴く人に「やる気」を起こさせてくれる。同じ弦でどうしてこうまで違った音量が出せるのか不思議でならない。しかもこの曲はリタルダンドとア・テンポとが交互に何度も繰り返されるのが特徴だが、ピアノとぴったり息があって、そこに少しのズレをも感じさせない。 恐らく演奏中の二人は心拍数まで おんなじ・・・になってるのではなかろうか? それにしても最近の成道さんのヴァイオリンはデヴュー当時と比べると格段の違いがあるように思うのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | ハンガリア舞曲 第4番 (ブラームス) |
1833年に生まれ、1897年64歳で死去するまでの間にブラームスが作曲した曲は管弦楽、ピアノ曲、合唱曲と数限りなくあるが、それぞれの年齢で遭遇したいろいろな事がら と照らし合わせて、ああ、この曲はこんな環境の中で創られたのか・・・などと想像を逞しくしながら聴いていくと、よりいっそう曲そのものの味わいも判って興味深い。 ことにこのハンガリア舞第二番の胸を締め付けられるような旋律を聴くと一体この時期 彼にどんなことがあったのだろう?と詮索したくなるのは単なるナカダの好奇心なのだろうか?? 音楽辞典によると、1852年〜1869年となっているから29歳頃からの作品らしい。 その頃、ブラームスはいろいろ恋の遍歴もあったりして、なるほどと肯かれることが多い。 「すべての曲種にわたって、ブラームスの音楽にはしばしばハンガリーのジプシーの音楽の手法が認められる。しかし、それと並んで、プロテスタントのコラールに影響されたところも多々ある」・・・と音楽辞典にも書かれているが、この第二番、まさにその通り。 成道さんのヴァイオリンはジプシー音楽の魂そのもの。 (彼の「ツゥイゴイネルワイゼン」が私達を魅了するのも同じ理由からだと思うのです。) ブラームスの楽曲は全体に教会音楽の敬虔な感じが流れ、聴くひとに「神の存在」を思い起こさせずにはおきません。聴いていて自ずと涙があふれ出るのはそういうことが原因なのでしょう。そしていつも、どんな時も敬虔であり、謙虚さを失わない成道さんの、その「人となり」・・・そこからすべては始まっている。・・・そんな気がしてならないのです。 それにしてもこんな美しい旋律が人間の手で創られたなんて!。初めてこの曲を聴いたときの心の震えが忘れられません。そして成道さんのヴィブラートはこの曲の哀調をいやが上にもかきたてるのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベマリア (シューベルト) |
グノーの、絞り出すような祈りの旋律に比べ、シューベルトの同名のこの曲はあくまでも優美な、そう、例えていうならば「清純そのものの・・・軽井沢あたりのお嬢様が(もはや今の時代には不在か?多分いないでしょうねえ。ま、古き佳き時代の・・・とでもしておきましょうか。)可憐に咲く白百合のかたえで、跪きつつ神に祈りを捧げる・・・の図」 って感じがするのです。 そこに流れるのは「哀しみ」とか「心の痛み」とかの暗さではなく、あくまでも美しく、明日への希望、そして未来への夢・・・それらを神に願うという・・・。成道さんの演奏にはそういった清純さが感じられ、透明な通奏音は聴く者をしていつしかみずからを「内省の世界」へといざなうのです。 ジャケットに成道さんの訳詩が出てますが、ほんとうに綺麗ですねえ。 ナカダはこの曲の旋律そのものも好き ですが、伴奏にも心惹かれます。イントロを聴くとつい歌いたくなるのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーク ヴァイオリンソナタ (第3番) |
グリーグの音楽から感じられるもの・・・それは北欧の厳しい自然。そして気温の低さが自ずと導く寂しさ・・・。昔からそうだった。グリーグの生まれがノルウエーと知っての先入観だったのかもしれないが、でもあの「ペルギュント」の中の「ソルヴェーグの歌」など、どう考えても暖かい温暖な気候とは結びつかない。 帰らぬ恋人を待ち続ける歌だけど、そこにあるのは「絶望」乃至は「恨み節?」。 しかしそれが極めて流麗に歌い上げられている・・・というところがグリーグさんの芸術性の高さというものだろう。 このヴァイオリンソナタにしても同様のことが言えると思う。 成道さんの手にかかるとそれはより一層鮮明なものとなり、グリーグ独自の「冷え冷えとした大気の中で自分自身の魂を透かし見るような」、旋律が繰り返し心を揺さぶる。 成道さんの最近の演奏では、その曲、その曲によって全然音色が異なって聴こえるような気がします。強弱のみならず音色のコントロール・・・といいますか、だからこそ、聴く者は共に泣き、共に酔うことが出来るのではないでしょうか? ついでにもう一つ。グリーグは生まれはノルウエーですが、ご先祖はスコットランド系の血を引いていたようで、そう言われてみれば何となく納得できるような気がしますね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロンドンデリーの歌 (アイルランド民謡) |
さあこれでいよいよラストです。この歌は「ダニーボーイ」のほうが曲名としては知られているかもしれません。 いろんな訳詩がありますが、長い年月いつくしみ育てた息子が手元を離れ巣立って行く、母親の哀しみを歌い上げた歌詞が一番ぴったりするような気がします。 「我が子よ いとしの汝を 父君の形見とし 心していつくしみつ 今日まで育て上げぬ 旧き家を巣立ちして 今はた汝はいずこ ・・・・」と続く。 成道さんの音色にはそういう哀調がよく出ていて心をうたれます。そしてクライマックスの力強さは歌詞の終わり近くの「ああわれも強くたちて 我が家の誉れを護らん」という、母親の決意めいたフレーズそのままに、奏でられ、同じく息子持つ身のナカダとしては「ジーン」と来ずにはいられないのです。 私達は過去の体験のなかにその時代流行ったメロディをからませていることが少なくありません。皆さんはこのメロディからどんな幻想がうかびあがるのでしょうか? どの曲もそれぞれ優劣つけ難く素晴らしいのですが、このアイルランド北部の、いかにも素朴な、それでいて高い気品の感じられる民謡。これをラストにもって来たという成道さんの意図にはきっとそれなりの理由がおありだったと思われるのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終わりに | 最後まで読んで下さったあなたへ・・・ ほんとうにありがとうございました。 おいおいまた手を加えてナットクの行くエッセイに仕上げたいと思ってますので、お暇の夜にはいつかまたこの部屋のドアのノブを回してくださいね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 (プログラムに金文字でサインしていただきました)
(プログラムに金文字でサインしていただきました)